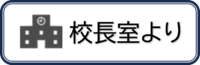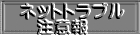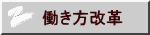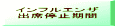お知らせ
埼玉県では、自転車に乗る際に自転車保険に入ることがが推奨されています。自転車保険のちらしを掲載します。 ちらしはこちら
埼玉県教育局より保護者の皆様へ「お子さんのスマホ大丈夫?」のリーフレットが届きました。詳細はこちら
3年生による英語での学校紹介のページができました。ぜひ、ご覧ください。 紹介ページはこちら
<重要なお知らせ>
来年度の学級編成に関わることから、今年度中に本校から転出する・または転出の見込みであることが分かった場合は、すぐに教頭までご連絡ください。第四中学校電話 048-477-6053
埼玉県教育委員会の不登校支援「親の会」のリーフレットが届きました。詳細はこちら
令和5年10月30日 <試行版 新しい「生活のきまり」>が、臨時生徒総会で承認されました。令和6年3月までの試行を予定しています。 詳細はこちら
中学生・高校生対象 SNS相談窓口のご案内 相談したいことがあったら。
SNS相談室リーフレットはこちら ☎️各種相談窓口一覧はこちら
新座市教育委員会より「自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう」
ヘルメットの着用は、令和5年4月から、法律で、すべての利用者の努力義務となりました。
(リーフレットは、自転車乗車時のヘルメット着用について)
↑埼玉教育振興に関する大綱知事メッセージは、
コバトン&さいたまっちをクリック
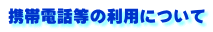
〇新規のお知らせ
| 教育内容のページ | |
| 年間行事予定はこちら | |
| 結果発表のページはこちら | |
| 📓R6.4.19 PTAのページ更新(PTAサポート活動概要)を掲載しました |
PTAのページ |
| 学校評価のページ | |
| 📚R4.12.15 クローバーの会(読み聞かせ)でメンバー募集中です | 学校応援団のページ |
〇給食の更新情報
| 🍚R6.4.12 4月食育Information,献立表を掲載 | 給食のページ |
| 🍚R6.4.19 4月18日までの給食写真を掲載しました |
最新の更新記録
〒352-0004 埼玉県新座市大和田4丁目17番地1号
Tel 048(477)6053 Fax 048(482)0134
{{counterChar}}
周辺の学校のようす
おすすめの図書
by edumap